年間で大損したら確定申告を検討しよう!
みなさん、今年は利益を得られそうですか?
「損失でてるよ!この野郎!」と思われた方。すみません m(_ _)m
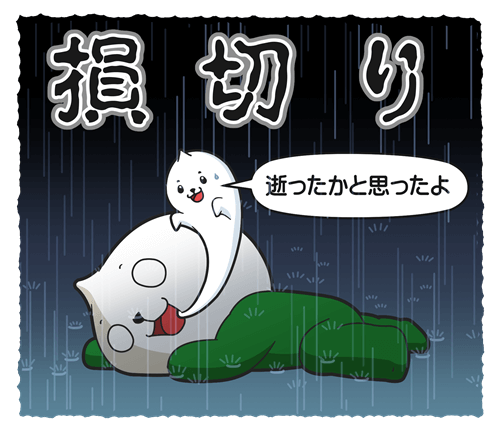
年間で損失を出した場合、
確定申告をすると節税になるかもしれません!
という「損失の繰越控除」に関する話です。
損失の繰越控除とは、発生した損失を以後3年繰り越し、次年度以降の所得を減らすことができる制度です。
初心者の方向けに、株式等の売却損が発生した際の節税方法をわかりやすく解説します。
監修者プロフィール
こちらの記事はカブスルが書いた原稿を基に、元税務署職員の平井 拓さんに監修・リライトを行って頂きました。
平井さんはマネーの達人で税金に関するコラムを執筆されています。
初心者にも分かりやすいコラムが人気ですので是非チェックしてみてください!
目次
確定申告とは?

確定申告は、1年間で発生した所得を計算し、所得金額に応じて算出された税金を国へ納める手続きをいいます。
確定申告は納税者が自主的に行わなければならず、所得を得た翌年の2/16~3/15の間に確定申告書を税務署に提出することになります。
2025年分(令和7年分)の申告時期は、2026年(令和8年)2月16日(月)~3月16日(月)です。
所得税(確定申告書等作成コーナー)by 国税庁
会社員や公務員の場合、勤務先の会社等が「源泉徴収」と「年末調整」により、税金を代わりに納めるので、確定申告をしたことがない人も多いかもしれません。
しかし、投資によって得られた利益は年末調整の対象外となっているため、投資の状況次第では確定申告手続きが必要です。
ワンポイント
証券会社は「特定口座/源泉徴収あり」と「特定口座/源泉徴収なし」を選択できます。
「源泉徴収あり」を選んだ方は、証券会社が納税者に代わって税金を納めてくれるため、確定申告を自分で行う必要がありません。
ただ、確定申告が不要な方でも確定申告をすることは可能ですし、「源泉徴収あり」でも確定申告を行った方がお得なケースも存在します。
「源泉徴収なし」を選択している場合、株の売却益など、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要になります。※
※給与が1か所(年末調整済み)で収入2,000万円以下のサラリーマンは、給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下なら、所得税の確定申告を省略できる特例があります。
株式を売却したことで確定申告が必要になるかを確認したい方は、参考記事をチェックしてください。
確定申告で「損益通算」すると得になるケースがある
大きな損失が出ている場合、確定申告で同年中に発生した損失と利益を損益通算することで、損失をリカバリーできます。
損益通算は利益と損失を相殺することをいい、証券会社の特定口座内の損益については、証券会社が自動で計算してくれます。
参考までに
たとえば、A証券会社で利益、B証券会社で損失が発生しているケースにおいては、確定申告を行うことでA証券の利益とB証券の損失を損益通算することが可能です。
- A証券:30万円の利益
- B証券:10万円の損失
上記のケースで確定申告を行った場合、損失10万円が利益30万円と相殺されますので、年間の利益は20万円に減少します。
譲渡所得税は利益に対して課される税金ですので、利益が減る分だけ納税額も少なくなります。
損失額が利益額を上回れば、譲渡所得税はゼロとなりますので、損失をリカバリーするためにも損益通算の活用は不可欠です。
「特定口座 源泉徴収あり」で取引している人は原則確定申告は不要ですが、取引している証券会社ごとで利益と損失が発生しているときは、確定申告を行うことも検討してください。
年間で損失が出ている場合は「繰越控除」ができる
損失の繰越控除とは、発生した損失を以後3年繰り越し、次年度以降の所得を減らすことができる制度です。
譲渡所得税は利益に対して課される税金であることから、株式等の売却損が発生している場合には、原則 確定申告は必要ありません。
しかし、売却損が発生しているケースでも、確定申告を行うことで損失額を最長3年間繰り越せますので、売却損を申告することも選択肢(損失の繰越控除)になります。
カブスルはリーマンショック時(2008年)に発生した損失額を確定申告書に記載し、繰越控除を利用しました。2009年は利益がでたので確定申告し節税になりました。
損失を繰り越すって何?
「損失を繰り越す」なんて言葉は、意味が分りづらいですよね。
カンタンに言えば、今年の「損失」を、翌年以降の「利益」と「相殺」するための手続きです。
ワンポイント
- 2025年 年間の売却益 -50万円
- 2025年の確定申告を行う(損失の繰越)
- 2026年 年間の売却益 +80万円
- 2026年の確定申告を行う
- 繰越控除の適用(相殺) +80万円-50万円=+30万円
- 2026年の売却益は +30万円に圧縮(節税)
上記のケースでは、2025年から繰り越された50万円の損失と2026年の80万円の利益を相殺したことで、利益50万円に対する税金を節税することができました。
参考までに
- 繰越控除をせずに+80万円の場合
80万円 × 20.315%(税率) = 16万2,520円 - 繰越控除によって+30万円の場合
30万円 × 20.315%(税率) = 6万945円
どうでしょうか?
譲渡損失の繰越控除を適用したことで、 10万1,575円も税金が安くなります。
繰越控除は損失額を3年間繰り越せますので、翌年に利益が出ていなくても相殺できるチャンスはあります。
ワンポイント
- 2025年の売却損 -100万円
- 2025年の確定申告を行う(損失の繰越)
- 2026年の売却益 +30万円
- 2026年の確定申告を行う
- 繰越控除の適用(相殺): +30万円-30万円=0円
- 2026年の売却益は損失額を控除したことで 0円に
※ 損失の残額-70万円は翌年に繰り越し
- 2027年の売却益 +50万円
- 2027年の確定申告を行う
- 繰越控除の適用(相殺): +50万円-50万円=0円
- 2027年の売却益は損失額を控除したことで 0円に
※ 損失の残額-20万円は翌年に繰り越し
- 2028年の売却益 +50万円
- 2028年の確定申告を行う
- 繰越控除の適用(相殺): +50万円-20万円=+30万円
- 2028年の売却益は損失額を控除したことで +30万円に圧縮
譲渡損失の繰越控除を適用した場合と、適用しなかった場合の税金を比較してみますと、
- 損失の繰越控除を適用した場合
30万円 × 20.315% = 6万945円の税金が発生 - 損失の繰越控除を適用しなかった場合
130万円 × 20.315% = 26万4,095円の税金が発生
どちらがお得かは一目瞭然ですね (  ̄∇ ̄)
損失を繰り越すには確定申告が毎年必要
譲渡損失の繰越控除の制度を利用することで、損失額は最長3年繰り越すことができますが、繰越控除を適用するためには確定申告が必須です。
繰越損失額を翌々年に繰り越す場合についても、翌年の確定申告で損失額を繰り越す意思表示をしなければならないので注意してください。
ワンポイント
最大で3年間 繰越控除を受ける場合、4年連続で確定申告をすることになります。
損失額を繰り越したいときは、取引がない年分においても確定申告が必要です。
なお、繰越控除の適用は任意ですので、株式投資を完全に終了する場合には、わざわざ確定申告をしてまで損失の繰越控除を適用するメリットはありません。
注意!健康保険料が増額される可能性がある
では、損失が発生した場合は、とりあえず確定申告をした方がいいんだよね?
譲渡損失の繰越控除を活用できるケースであれば、適用することで節税になります。
しかし、トータルの損得で考えた場合、確定申告を行った方がお得になるとは言い切れません。
損得の判断が難しい理由としては、確定申告で損益通算を行うと、投資によって得られた所得が給与や公的年金などの他の所得とともに、保険料の算定対象に加算されるからです。
問題になりやすいのは健康保険料
「国民健康保険料」など健康保険料は、株式投資などを含めた所得をベースに算定します。
年間の所得金額が増加すれば、国民健康保険料が上がることもありますし、 保育料や高額療養費、児童手当やその他の行政給付などに影響が及ぶ可能性もあります。
また、扶養に入っている人については、所得金額が一定基準を超えることで扶養から外れるケースも出てくるので注意が必要です。
税額上の還付分 < 保険料等の増額分などが上回る
確定申告により上記の構図になれば、結果的に損をします。
損失額や還付される税額の金額、加入している健康保険の種類、その他の行政手当の受給状況などにより損得は分かれますので、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
確定申告時期が近付くと、無料相談会が開催される場合が多いです。
ただ無料相談会は人気があるので、出来れば無料相談会前に税務署で聞いた方がいいと思います。
NISA口座の損失は繰越控除の対象外
2024年からはじまった新NISAは、最大1,800万円まで非課税で資産運用することが可能です。
ただNISAで発生した譲渡損失は、繰越控除の対象外なので注意してください。
利益が発生したときはNISAを活用した恩恵を受けられる反面、損失が発生したとしても、利益と相殺することはできない点は覚えておきましょう。
意外と知られていない譲渡損失の繰越制度
今回は「損失」という 嫌~なお話でしたが、実はコレ、知っておいた方がよい話です。
確定申告をすれば損失を3年間繰り越せる
この特例はとっても役に立つ制度です。
みなさんは手元に「塩漬け株(みなし損失)」はありませんか?
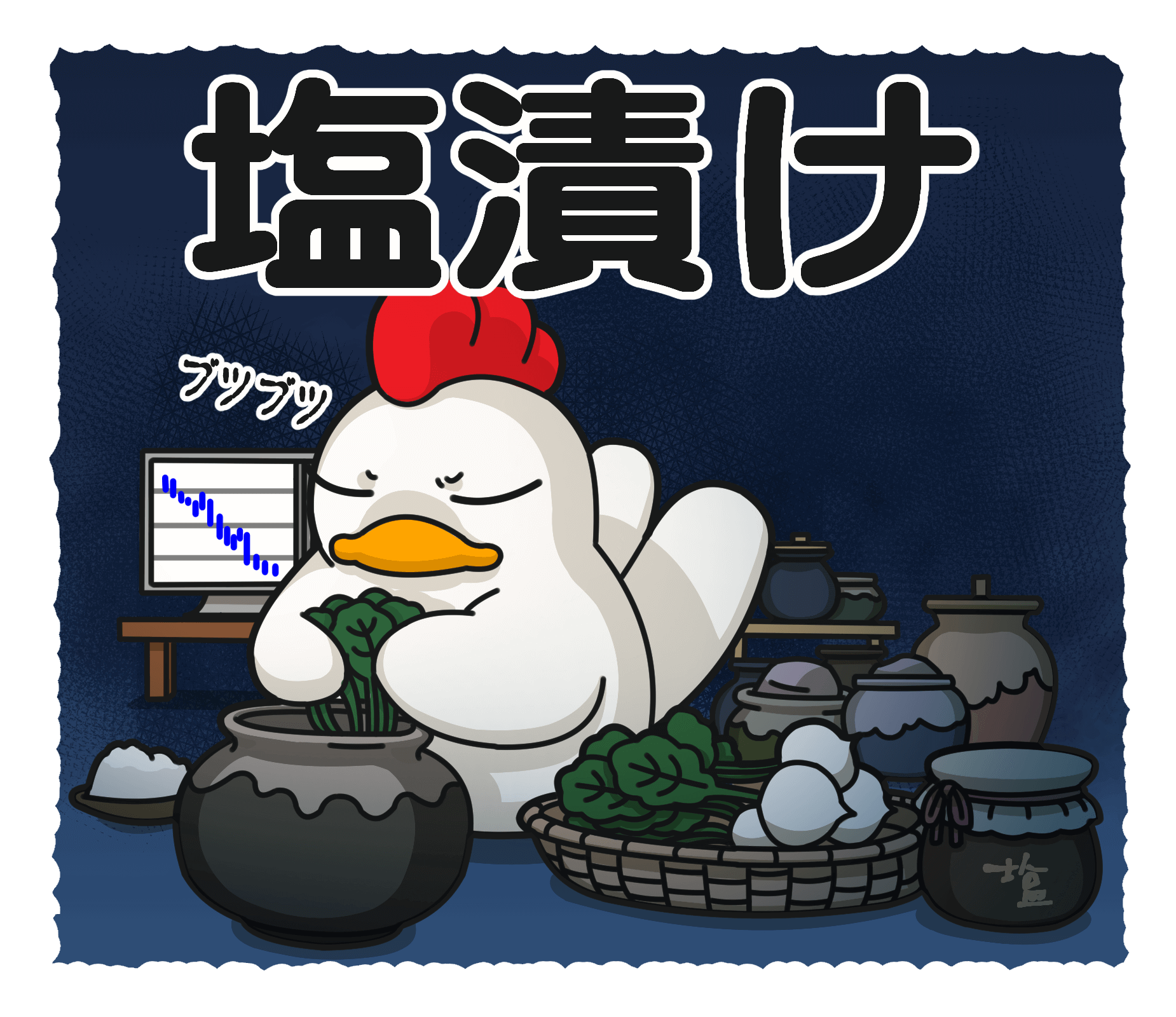
塩漬け株とは、損失が出ている銘柄の株価の回復を待って保有し続けている株のことです。
売ることができず投資資金が凍結されている状態ですが、塩漬け株を売却して損失を確定することにより、凍結していた投資資金が解放されます。また、その損失は最大で3年間、その後の利益と相殺(節税)できます。
回復が思わしくない塩漬け株は思い切って売り、回復した投資資金により新しい株を買った方が、より良い投資ができるキッカケになります。
参考までに
損失が出ていた方で「損失の繰り越し控除」の申請をしていなかった方。
「確定申告」自体をしていなかった場合でも、損失が出た年を含め過去分について「期限後申告」で損失の繰越控除を適用できるケースがあります。
期限後申告を検討するときは、お近くの税務署に具体的な取扱いを確認してください。
ただし、上記で紹介したとおり、場合によっては保険料などの関係で全体的に損する場合もありますのでご注意ください。
(参考)株式投資の確定申告について相談したいときは?
まずは税務署に相談してみましょう。
どの程度の相談に乗ってくれるかは、相談内容と担当者の度量によると思います。
確定申告時期が近付くと無料相談会が開催される場合が多いですが、混雑することが予想されますので、無料相談会前に税務署で聞くことも検討してください。
税務署や無料相談会で相談を断られたら?
一部の相談会では「株式譲渡益に関する相談はできません」としているところがあるようです。
その際は、税理士さんに相談しましょう。
税務相談は、有償無償を問わず税理士資格を持っていないとできません。※税務署職員など一部例外あり
個人のスキルを売買する「ココナラ」では、税理士さんが税金の相談を受けていますので、そちらを利用するのも選択肢の一つです。
こちらの記事はカブスルが書いた原稿を基に、元税務署職員の平井 拓さんに監修・リライトを行って頂きました。
監修者プロフィール
元税務署職員 平井 拓さん
12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。
税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。
脱税は嫌いですが、節税は好きです。
少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。
平井さんはマネーの達人で税金に関するコラムを執筆されています。
初心者にも分かりやすいコラムが人気ですので是非チェックしてみてください!
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。

