株式投資の歴史
株式投資が始まるには株式会社の誕生が必要なわけですが、
株式会社ができた
時代背景(歴史)を知ろう
世界ではじめて株式会社を設立したのはどこなの?
というと、
1602年にオランダで設立された
「東インド会社」
が世界ではじめての株式会社となります。
東インド会社が株式会社の原点
時は、ヨーロッパの「大航海時代」。
各国との貿易が盛んではありましたが、海賊などもとても多い時代でした。
もちろん自然の猛威や、当時の船の規模・装備品だけでは航海をするのに危険が伴いました。
「航海に成功すれば、貿易で大もうけ。航海に失敗すれば、大損」
そんな時代が大航海時代です。
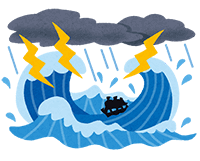
一つの会社が航海をし、成功すれば大もうけ、失敗すれば大損・・という博打的な経営を当時は行なわないといけませんでした。
しかし、一つの会社による博打的な航海は資金繰りがとても難しく、周りからの信用も得がたく、マトモな経営はできません。
そこで一度の航海につき、周りからお金(出資金)を集めて
- 航海に成功すれば貿易で得た利益の分け前を分配する
- 失敗すれば集めた資金は没収となる
そんな仕組みが生まれました。
利益を分け前として分配しますので航海が成功した場合の利益は減りますが、その代わりに航海に失敗した場合でも損失を分散できるようになったのです。
非常に合理的なこの仕組みを組織化した東インド会社が株式会社の原点と言われています。
ワンポイント
- 出資する人々は自分が良いと判断した船を選び(企業)
- その船にお金を出して(投資)
- 出資したことを証明する紙をもらい(株券)
- その会社が貿易を成功させれば(業績の好調)
分け前をもらえた(配当金)わけですね。
当時、8つの会社が集まりできた東インド会社は約200年間続きました。
平均で年利25%、最大で年利75%という高パフォーマンスを叩き出していたそうです。
日本初の株式会社は?
日本初の株式会社は、明治6年に設立された「第一国立銀行」という民間銀行になります。
ちなみに東証、大証が設立されたのは明治11年。
戦争により一時的に閉鎖されましたが昭和24年よりまた再開されました。
(証券教育広報センターより)
第一国立銀行は後に第一銀行と改称し、さらに日本勧業銀行と合併し、第一勧業銀行となりました。さらにバブル崩壊後の銀行再編で、日本興業銀行、富士銀行と3行が合併し、今のみずほ銀行に至っています。(renbajinharuhiさんより)
坂本龍馬は同様の事業を行っていた!
正式な株式会社ではありませんが、明治維新の立役者である「坂本龍馬」が株式会社同様の事業をすでに行っていました。
ワンポイント
- 坂本龍馬は薩摩藩に「営利」を説いてお金を出させて(出資)
- 船を買い、亀山社中(後の海援隊)を立ち上げて(企業)
- その船を使い貿易で得た利益を薩摩藩に還元(配当金)
していたそうです。
当時の株式投資は「配当金」が目当てでした。
純粋に好業績を出し、配当金をたんまりくれる会社に株主は出資していたわけですね。
企業も会社を運営するために株券を発行して資金を集め、利益を株主に還元しているんです。
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。
